更年期に【痔】が増えるのはなぜ?今日からできる予防セルフケア5選
座っているとお尻が痛い、排便のたびに出血があるなど、つらい痔に悩まされていませんか? 女性は痔になりやすい傾向があり、更年期以降も痔を経験する人が少なくありません。つらい痔を繰り返さないために、痔の種類や原因、そして予防や再発を防ぐためのセルフケアを紹介します。
◆あわせて読みたい
1.つらい痔の症状

痔とは、肛門やその周囲に起こる病気の総称のこと。代表的なのは「いぼ痔」「切れ痔」「痔瘻(じろう)」の3つです。
いぼ痔は肛門の血流が悪化し、血管が膨らんで腫れるもの。腫れが肛門の内側にできると出血しやすく、外側にできると痛みを伴いやすい傾向があります。また、内側が腫れている場合、進行すると腫れが肛門外へ飛び出して戻らなくなることもあります。
切れ痔は硬い便や下痢によって肛門の一部が切れてしまう状態のこと。排便時の鋭い痛みが特徴です。
痔瘻は肛門の奥に炎症が起こり、膿のトンネルができる病気で、基本的には手術による治療が必要です。発熱や座っていられないほどの痛みなどが出ることもあります。
いずれも生活の質を下げてしまうため、早めの対処が大切です。
2.更年期に痔が増える原因は?
更年期には体のバランスが変化し、痔の症状が出やすくなる要因がいくつも重なります。ここでは代表的な3つの原因を見ていきましょう。
①肛門括約筋の衰え
肛門括約筋は、肛門を締めたり緩めたりする働きを持つ骨盤底筋の一つです。女性の場合、肛門括約筋が加齢によって衰えて肛門に負担がかかったり、出産経験などによって傷ついて硬くなったりしやすい傾向があります。
これにより排便がスムーズにできなくなり、排便時に余計ないきみが生じやすくなります。肛門に強い圧力がかかると、肛門周囲の血流を妨げてしまい、痔のリスクが高まるのです。
②ホルモンバランスの変化
更年期になると女性ホルモンのひとつであるエストロゲンが減少し、自律神経が乱れやすくなります。自律神経は腸の働きにも関与しているため、自律神経が乱れると腸のぜん動運動も乱れ、便秘や下痢になりやすくなるのです。
便秘や下痢は肛門に過度な負担をかけてしまう大きな要因です。そのため、更年期以降に便秘や下痢を繰り返していると、痔になる可能性も高くなります。
③下半身の冷え
冷えも痔を招く大きな要因の一つ。特に、下半身が冷えると骨盤や肛門付近の血流が悪くなり、血管がうっ血しやすくなります。
また、体温調節の機能も担う自律神経の乱れも、血行不良を招き冷えにつながる要因に。ほかにも、冷房の冷気や冬場の低い気温などの影響で痔につながることもあります。
3.痔の予防のための対策5選
痔の予防や再発を防ぐためには生活習慣を見直して腸内環境を整えることが大切。具体的な対策方法を5つ紹介します。
①肛門括約筋を鍛える
痔を防ぐには、肛門括約筋を意識的に鍛えることが効果的。肛門括約筋を鍛えると排便時のいきみの軽減や、肛門周辺の血流改善などの効果が期待できます。
肛門括約筋を鍛えるには、骨盤底筋体操がおすすめです。
<骨盤底筋体操のやり方>
1.仰向けになり、両膝を軽く立てて肩幅程度に開く
2.尿道・肛門・膣をきゅっと締める
3.力を抜いて緩める
これを2〜3回繰り返しましょう。また、肛門などをゆっくり締めて3秒程度停止し、ゆっくり緩める方法もあります。この場合は、慣れてきたら締める時間を少しずつ延ばしましょう。
骨盤底筋体操は継続して行うことが大切です。就寝前のルーティンに取り入れるなど、習慣として行いましょう。
②排便のリズムを整える

毎日の排便リズムを整えて、便秘を防ぐことも痔の予防につながります。朝起きたらコップ1杯の水を飲む、朝食をしっかり食べるといった習慣で腸のぜん動運動を促し、自然な排便を促しましょう。
また、便意を感じたら我慢せずトイレに行くこともポイント。我慢しすぎると便が硬くなり、切れ痔の原因になってしまいます。
③下半身を冷えから守る
冷えによる肛門周辺の血流悪化を防ぐために、日常的に下半身を温める工夫をしましょう。膝掛けやレッグウォーマー、カーディガンなどを活用し、外出先でも体を冷やさないよう意識することが大切です。
また、入浴はシャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かりましょう。体が温められることで血流が促進されるほか、腸の動きも促進されて便秘の改善が期待できます。心身のリラックス効果もあり、自律神経を整えることにもつながります。
④食物繊維を積極的に摂る
痔の最大の予防策は、自然でスムーズな排便を実現すること。そのためには、腸内環境を整えることが大切です。
腸内環境を整えるために欠かせないのが食物繊維です。野菜や果物、海藻、豆類などに豊富に含まれる食物繊維には、大きく分けて不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があります。
野菜や豆類に多く含まれる不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸のぜん動運動を活発にして排便を促す働きがあります。
一方、海藻や果物、オートミールなどに豊富な水溶性食物繊維は、水分を含んで便を柔らかくするほか、善玉菌のエサとなって腸内環境を整える役割を持っているのが特徴です。
また、腸内の善玉菌が水溶性食物繊維を分解して作り出す短鎖脂肪酸は、腸内環境を整え、便通改善に役立ちます。
例えば、朝食にオートミールを取り入れる、夕食に海藻サラダをプラスする、味噌汁に複数の野菜を入れるなど、小さな工夫を積み重ねて食物繊維を摂りましょう。
⑤サプリメントを活用する

忙しい日々の中で、食事だけで腸内環境を整えるために必要な栄養素を摂るのは難しいもの。そんなときは、サプリメントを上手に取り入れるのも一つの方法です。
サプリメントの中には、乳酸菌やビフィズス菌、オリゴ糖、食物繊維など腸内環境を整える成分を含むものもあります。普段の食事内容を振り返り、不足しがちな成分をサプリメントで補うことで、腸内環境の改善につなげましょう。
ただし、サプリメントはあくまでも補助的なものです。先にご紹介したセルフケアを組み合わせながら活用しましょう。
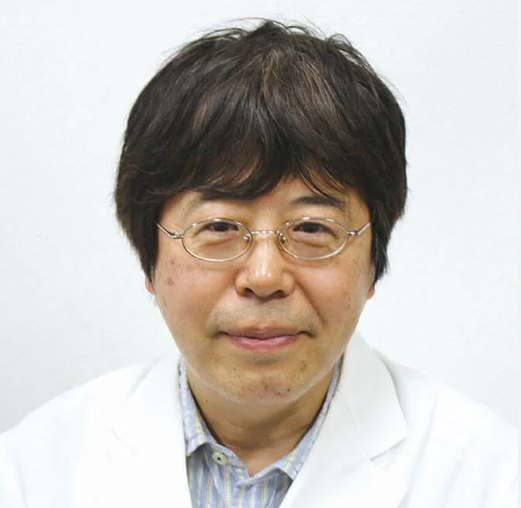
1988年、東京大学医学部卒業。独自の無麻酔・無痛大腸内視鏡検査法「水浸法」を開発。大腸内視鏡6万件以上無事故のベテラン医師。大腸がん予防から始まった腸内細菌や乳酸菌にも造詣が深く、菌のパワーを使って健康になる方法を各所で伝授し続けている乳酸菌の専門家。サプリメント「今日から腸活!」の監修も務める。
編集/根橋明日美 写真・イラスト/PIXTAほか
◆こちらの記事もおすすめ
▶美味しすぎる&腸活にもなる「絶品餃子レシピ」!料理家・真藤舞衣子さんに聞いてみた!
